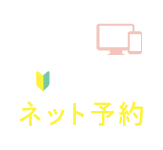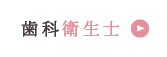3.形や生え方の違い
人間と動物では形や生え方にそれぞれ特徴があり、動物の中でもいろいろな種類がいます。
まず形ですが、肉食動物は肉を切り裂いて食べるため、鋭く尖った歯を持っています。
逆に草食動物は草や木の実をすり潰すので平らな歯を持っています。
人間は雑食で両方とも食べるので両方の機能が使える歯となっています。
そして生え方も人間と動物では大きく違います。
人間は子供の頃に乳歯が全部で20本生え、徐々に永久歯に生え変わります。
永久歯は全部で28本、親知らずが4本全て生えれば32本となります。
例えばサメは全部で200本ほど歯が生えています。
しかもそれらの歯は2,3日ごとに新しい歯に生え変わります。
現在使っている歯の後ろに6〜10列ほど予備の歯が控えているのです。
いつも新しい歯で獲物を捕らえることができ、これなら虫歯にもならずに過ごせますね。このように何度も歯が生え変わる動物を多生歯性と呼ばれています。
また、げっ歯類といわれるウサギやネズミ、カバなどの犬歯(八重歯といわれている歯)は一生伸び続けます。だいたいは3〜4日で約1ミリずつ伸びていきます。
硬いものを食べることで伸びている歯をすり減らしているのです。
象の場合は大きな臼歯が上下左右に1本ずつの計4本しか生えていません。
ただ1本が3〜4Kgもあり、表面は凸凹しています。
硬い木などを食べるため大きくて丈夫な歯ですりつぶして食べます。
生活していく中で歯はどんどんすり減っていくのですが、ある程度の薄さになると生え変わります。
生涯で6回生え変わるのですが、人間のように下から垂直に生えてくるわけではなく、水平交換といって奥にある臼歯が脱落するという形になります。
それなので歯がなくなる時期がありません。
4.歯のない動物?
動物にはほとんど歯がありますが、なかには歯が生えてない種類や、一部だけ生えている種類もいます。
歯がない場合はどうやって食べているのでしょう?
アリクイやカメ、鳥類は歯が生えていません。
アリクイは名前の通りアリを食べるのですが、舌がネバネバしていてそこにアリをくっつけて運んだり食べたりします。
カメは顎の肉がとても硬くなっていてそこで食べます。
鳥は食べ物を丸呑みします。ペンギンが魚を丸呑みしているのを見たことがありませんか?
丸呑みすると消化が大変なので、鳥類には消化器官に「砂嚢」という部分があります。そこに砂や小石を蓄えてそれで食べ物をすり潰すのです。
小鳥などはくちばしで木の実などをつぶして食べたりもします。
牛は、歯は生えているのですが、上の前歯だけ歯が生えていません。
草を食べるのですが、下の前歯と硬くなっている上唇で草を食いちぎって食べます。
また、カエルは下の歯がなく上だけ歯が生えています。
クジラは種類によって歯が生えているものと生えていないものがいます。
ハクジラとヒゲクジラの2種類いて、ヒゲクジラという種類は歯が生えておらず、ヒゲという角質の板で小さな餌を越してから食べます。
ハクジラには歯が生えているのですが数が不規則で、種類や性別により大きく差があります。
こう見ていくといろいろな種類がいますね。
人間も昔に比べて顎が小さくなったり、あまり噛まなくなったりしているので親知らずが昔に比べて生えなくなった人も多いです。
長い年月をかけて、進化の過程で変化していくのです。
5.最後に
人間と動物の歯の違いについて理解できましたか?
動物たちはそれぞれ食べるものが違うため、その動物にあった歯になっているんですね。
特に野生にいる動物は食べることができないと生死に関わってくるためとても大切なものなのです。
動物は折れたりしない限り虫歯にはなりませんが、飼われているペットとなると話は変わってきます。
虫歯や歯周病になる可能性は十分にあり、それが口臭の原因になったり、膿が出てくる原因にもなるためしっかりケアをしてあげましょう。
また人間は火を使うようになってこんなに虫歯ができるようになってしまいましたが、今から昔のように火を使わない生活になるなんてことはありません。
そして同じように生活をしていても、国によっては予防に力を入れていて虫歯になる人がとても少ない国もあります。
サメのようにどんどん新しい歯が生えてきたら虫歯にもならず、とてもうらやましいですが、もちろんそんなわけにもいきませんね。
毎日しっかり歯磨きをして、定期検診に行き、虫歯を作らないようにケアしましょう。